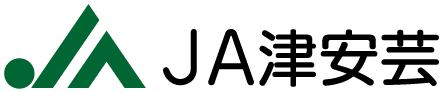2022.6.17
「飼料用米多収日本一」コンテストで東海農政局長賞(単位収量の部)受賞 三重・喜多義幸さん
河芸町で農業を営む喜多義幸さんは6月中旬、津市役所を訪れ、前葉泰幸市長に令和3年度「飼料用米多収日本一」コンテストで東海農政局長賞(単位収量の部)受賞の報告をしました。
コンテストは、飼料用米品種「あきだわら」「どんとこい」約7.3ヘクタールを作付けし、10アールあたり654キロと地域の基準単収と比べ高い収量を確保したことが評価され受賞となりました。
喜多さんの圃場は湿田で麦・大豆への転作には適していないため、飼料用米の作付けを10年程前から行い、ドローンによる病害虫防除やプール育苗などの生産コスト低減と効率的な飼料用米生産に取り組んでいます。

報告を受けた前葉市長は「様々な工夫が受賞につながった。今後の生産拡大に期待し、これからも若い世代に伝えてほしい」と話しました。

2022.6.6
麦刈り始まりました!!
6月3日から津安芸管内で小麦「あやひかり」の収穫作業が始まっています🚜≈꒱
今年の小麦は天候にも恵まれ品質良好◎
小麦は黄金色でとても綺麗~٩(´꒳`)۶
この時期にしか見れない景色ですね~🎵
晴天の暑い中での作業、休憩小まめに取ってくださいね(*´ω`*)👌

2022.6.3
【農機センター】草刈機無料点検会開催しました!
5月21日から各営農センターと育苗施設で草刈機無料点検会を実施しました。

農機センター職員が持ち込まれた草刈機を確認し、替え刃交換やエンジンの点検など行いました👀✨
期間中は122台の草刈機が持ち込まれました(`・ω・´)
プロの目でチェックしてもらうと安心しますよね😊👍
利用された方は、「初めて利用しましたが、丁寧に見てもらえて安心しました」と喜んでいました(*‘∀‘)

2022.4.15
タケノコの出荷が始まりました
津中央営農センター管内の片田集荷場でタケノコの出荷が順調に進んでいます。
本年産は、例年より降水量が少なく、気温が低い日が続き、昨年に比べてると集荷時期は遅くなっていますが、今年も品質は良好で徐々に集荷量も増えてきています╰(*°▽°*)╯✨
歯ごたえがあって美味しそう~(❁´◡`❁)
4月下旬の向けて出荷のピークを迎えますので、タケノコご飯などタケノコ料理をぜひご賞味ください♪

2022.1.28
2022新春中古農機展示会を開催
1月15日、農機センターは「2022新春中古農機展示会」を開催し、177名の方にご来場いただきました。
会場には、トラクタやコンバインなど大型機械から小型農機まで各種農業機械を展示し、来場者は農機担当者から農業機械の特徴や性能などについて説明を受けていました。
寒い中、ご来場いただきありがとうございました。

2021.12.17
大豆の収穫が始まっています!
空気が澄んだ冬空のもと、南河路営農組合が大豆の収穫作業を行っています。
汎用コンバインが、力強く大豆を刈っていきます。
今年は前年と比べて生育も順調で、鞘への実入りもいいそうです。
大豆の収穫の目安は、爪で押すと子実に少しあとがつく頃、また、ポキッと茎が折れるまで水分が低くなった頃が収穫適期とのことです。

2021.12.10
目ぞろえ会を開催
11月29日、いちご目揃え会・白ネギ目揃え会を開催しました。
目揃え会では、選別基準や出荷時の注意点など現物を見ながら確認👀
イチゴ・白ネギとも消費者へ良い品質のものを届けようと、生産者の意識統一を図りました。
今年も品質としては良好🌟
皆さんも管内で出荷された野菜や果物を見つけて、ご購入してみてくださいね~(^^)/

2021.11.11
南河路営農組合が麦の播種作業
11月初旬より、津中央営農センター管内の南河路地区で令和4年産麦の播種作業が始まっています。
南河路営農組合の矢代正則さんは、小麦「あやひかり」作付面積10ヘクタールの圃場を自動操舵装置が搭載されたトラクターで播種作業を行います。自動操舵は2年程前から導入。
同営農組合の矢代さんは「畝の直線性の向上や畝間がしっかりすることから、効率的・省力的で精度の高い作業ができる」と話ました。
小麦の栽培は、津地域農業改良普及センターやJA営農担当職員の指導や情報提供により取り組んでいます。

2021.10.19
人・農地プラン実質化に向けて
10月6日、河辺町自治会は、「人・農地プラン」実質化に向けて、河辺町集会所で自治会役員や稲作農家代表者、関係機関職員18名が集まり、河辺町の農業について話し合いを行いました。
5年後・10年後の地域の実情を農業委員から報告を行い、将来の地域農業の方針について話し合いました。
今後も、地区内全ての稲作農家へ現状を報告し、また意見を聞きながら地域農業の将来方針を決定し、「人・農地プラン」の実質化に向けて取り組んでいきます。

2021.10.11
南河路営農組合が小麦播種前に栽培研修会を開催
10月10日、南河路営農組合は地区の集会所で「小麦栽培研修会」を開催し、同営農組合や津地域農業改良普及センター、JA営農担当職員の8名が参加しました。
研修会は、同地域農業改良普及センター職員から、土壌の状態に合わせた土づくりや良好な生育を促すための排水対策など、播種前の準備から収穫作業までの説明を聞き、参加者全員で地域圃場の実態に照らし合わせての意見交換を行ないました。
最後には、小麦栽培以外の質問も受け付け、有意義な研修会となりました。